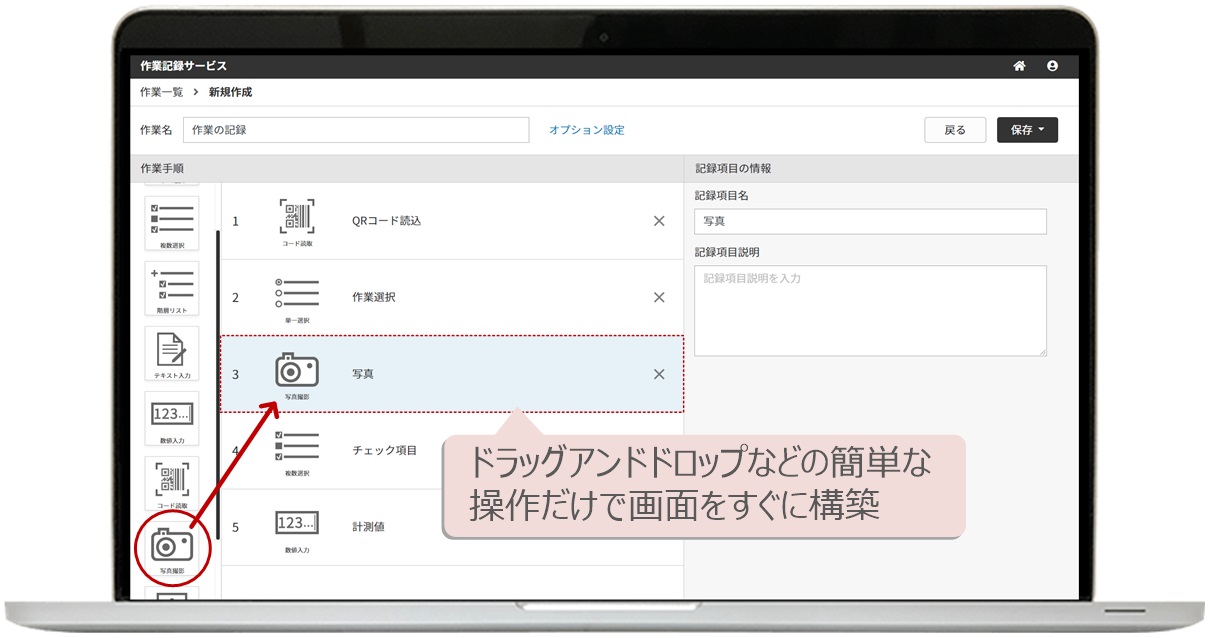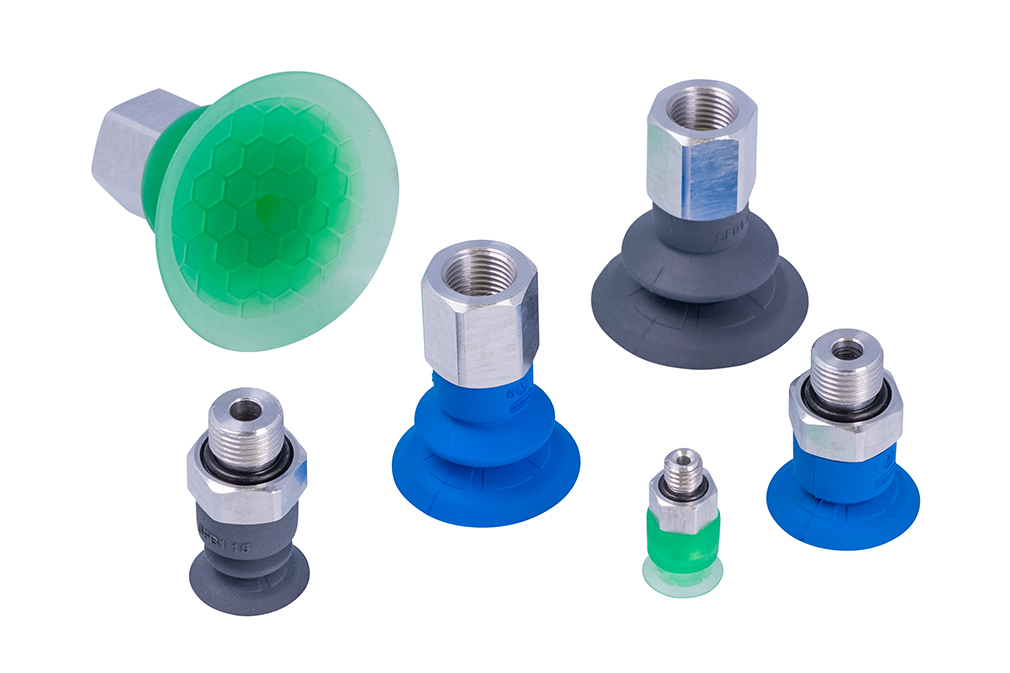改善は誰のために行うか
↓
工場でのあらゆる活動は、お客さまからのご要望に応えるために行っている。
「改善は誰のために行うか?」というシンプルな質問ですが、これにはいくつかの答があると思います。一緒に考えてみませんか?
自分のため…そうですね、いいと思います。自分で仕事をしていてすごく面倒くさかったりきつかったりということってありますね。そんなときに、いいアイデアを思いついて改善を実行したら楽に良いものができるようになったとしたら、それは嬉しいです。さらにその改善を上司の方がほめてくださったりすればなおさら嬉しいですよね。そして改善を実行する過程で方法を考えたり材料を選定したりといろいろ考えなければなりませんし、試行錯誤を繰り返すこともあるでしょう。これらは非常にいい経験になり、自分自身の能力を向上させてくれます。改善は明らかに自分のためになっています。
会社のため…それもその通りです。改善をした結果、楽に良いモノができるようになれば、それは生産性向上であり品質向上ですから、会社経営に対して大いなる貢献ができることになります。改善は会社のためにもなっています。
この二つはとても分かりやすい答です。多くの方がまずはこの答をされたのではないでしょうか。
しかし私はもう一つとても大切な答があると思います。それは「お客さまからのご要望に応えるため」という答です。
お客さまからのご要望に応えるため…これは意外と忘れがちなのですが、私たちが毎日工場で生産している製品はすべてお客さまの要望にお応えするために作られています。品質向上もコストダウンもリードタイム短縮もすべてお客さまに良いものを適切な価格でタイムリーにお届けするために行っているともいえるでしょう。工場はお客さまからのご注文がなければ全く動きません。つねにお客さまのご要望を意識して改善して、より高いレベルのご満足を頂くことが必要です。そう考えた時に私たちはどれだけお客さまのことを考えているかというと必ずしも十分とは言えないことがありそうです。
お客さまは私たちに何を一番に望んでおられるのか。品質? 納期? 価格? あるいはもっと別のこと?
ご注文いただいた製品を、自分たちができることを総動員してご満足いただけるようにお届けすること、これこそが仕事であり、チームプレー失くして達成することはできません。
改善とは、その総合力を引き上げる全社的な活動なのです。

日本カイゼンプロジェクト 会長 柿内幸夫
1951年東京生まれ。(株)柿内幸夫技術士事務所 所長としてモノづくりの改善を通じて、世界中で実践している。日本経団連の研修講師も務める。経済産業省先進技術マイスター(平成29年度)、柿内幸夫技術士事務所所長 改善コンサルタント、工学博士 技術士(経営工学)、多摩大学ビジネススクール客員教授、慶應義塾大学大学院ビジネススクール(KBS)特別招聘教授(2011〜2016)、静岡大学客員教授 著書「カイゼン4.0 – スタンフォード発 企業にイノベーションを起こす」、「儲かるメーカー 改善の急所〈101項〉」、「ちょこっと改善が企業を変える:大きな変革を実現する42のヒント」など

一般社団法人日本カイゼンプロジェクト
改善の実行を通じて日本をさらに良くすることを目指し、2019年6月に設立。企業間ビジネスのマッチングから問題・課題へのソリューションの提供、新たな技術や素材への情報提供、それらの基礎となる企業間のワイワイガヤガヤなど勉強会、セミナー・ワークショップ、工場見学会、公開カイゼン指導会などを行っている。
■詳細・入会はこちら
https://www.kaizenproject.jp/