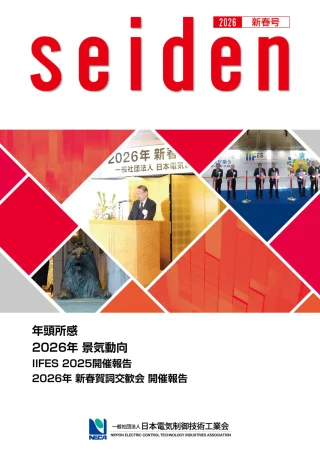- コラム・論説
- 2022年1月14日
【灯台番外編】私は今回のIIFES2025をどう見たか?展示会の位置付けは大きく変わった お祭りは主体的に楽しんだもの勝ちなのだ

IIFES2025が閉幕した。来場者数は4万5324人で、前回を3000人ほど上回った。目標の5万人には届かなかったが、総じて見れば大健闘だと思う。弊社もメディアと出展者という両方の面で参加したが、いずれの立場から見ても、今回はとても良く、次につながる可能性や手応えを感じることができた。
開催前と開催後で印象は大きく変わった
正直な話、前回開催の2024年から今回までの1年間、取材や営業で色々な企業や人にIIFESに対して出展有無や率直な意見を求めたところ、「今回は出展をしない」「内輪のお祭りのような感じ」「本当に来てほしいお客さんが来ない」といったネガティブな反応に出会う機会が多く、ユーザーをはじめ来場者側の人に聞いても「行きたいけど行けない」「予定はない」「IIFESって何?」など、距離を感じる機会も多かった。
また前々回のコロナ禍下の開催時に1万人台に落ち込み、前回もコロナ禍前には戻らなかったという定量的な事実があった。さらに、長年にわたってこの業界を支えてきた企業が出展しない、主要なプレイヤーも出てこないという状況もあり、弊社自身もネガティブな思考に傾いて会期を迎えた。
ただ実際、会期が終了し、振り返ってみれば、確かに金銭的に大きな出費をし、工数もかけたので費用的な部分は嵩んだ。肉体的にも精神的にも大変で、疲労困憊で消耗もした。会場とブースにつきっきりだったので残務も増えた。新聞の購読や新たな広告申込み、見込み客獲得といったリード獲得についても、そのような話はひとつもなく、それで言えば成果はゼロだった。
しかしながら、定量的な数字では表しにくい部分、人間関係の強化や新たな人脈、共創の土台づくり、六感をフルに活かして得たリアルな情報、多くの人との対話を通じた意見や視点、アイデアの入手、新たな発想や可能性のひらめき、大きなプロジェクトを完了させた達成感など、想像以上に大量の収穫があった。総じて言えば、出血は激しかったが、大成功で大満足だ。
リード獲得だけでいいのか?
展示会への出展は、営業やマーケティング部門の主導による「リード獲得の手段」として”だけ”見れば、費用対効果はデジタルマーケティングほど高くい。だから「出展しない」という判断も理解できる。しかし今回、自社でもチャレンジを多く行った結果、単に営業・マーケティングのためのリード獲得手段という視点だけで展示会を活用するフェーズはすでに終わったという結論に行き着いた。単に製品や技術を展示、紹介するだけでなく、逆に経営レベルで活用し、もっとアイデアを豊富に、手を変え品を変えて色々な取り組みを行い、次の成長のきっかけを作る場、共創を広げる場として活用することを考えていかなければならない。
実際、今回のIIFESで弊社が取り組んだことは、従来と同じく新聞紙面でIIFES特集を作成して会場とブースで新聞を配布することに加え、「モノヅクリステッカーコレクション」として18社に協賛いただき、各社オリジナルステッカーをブースで配布してもらい、ステッカーをきっかけとして協賛企業間の交流をしてもらった。さらに会期2日目の夜に「裏IIFES・FA交流会」を開催し、FA関連企業の約40社100人を招待し、出会いの場を提供した。前述の通り、新聞配布ではリード獲得の成果は出なかったが。ステッカー企画では協賛各社同士のつながり構築ができて良かったという声をもらったり、裏IIFES・FA交流会では「FA・製造業を盛り上げたい・語りたい」という意識が高い人々が集まり、競合や取引の有無関係なく意見交換したり、次の施策のアイデアを話しあったりと、弊社も含めて多くの共創の種を蒔き、第一歩となるきっかけを作れた。これは単なる営業やリード獲得ではなく、将来の事業成長のための土壌整備。このIIFESがなければこうした企画は生まれず、実施されなかった。その意味でもIIFESはとても良い機会だった。

来場者に寄り添う展示が増加
また前回開催時、このコラムで各社のブース出展内容について、「ソリューションやパネル展示ばかりで面白くなかった」と指摘した。これが大きな反響を呼んだようで、今回はコンポーネンツを軸に展示を行う企業が増えていた。しがない一意見を取り上げていただけて恐縮だが、今回改めてメディアの立場として各社ブースを回った印象では、最新技術の展示はもちろんだが、顧客に寄り添う展示が多く、素晴らしかったと思う。
例えば、前回、ソリューションを中心にかなり攻めた形の展示を行い、私がコラムを書くきっかけとなったオムロンだったが、今回はコンポーネンツを中心に展示し、さらにそれらの性能・機能を紹介するのではなく、それをより簡単に有効に使うためのやり方やツールを実機と一緒に体験できるという展示を実施。説明員には、そのツールの開発者を充て、実際に開発した人間がユーザーと話をしてリアルな生の声を聞くようにしていた。同社によると、途中経過ではあるが、ブースの滞在時間や説明員と話す時間は確実に増え、話の内容も濃く、色々な意見を聞けたという。単に「見せる」だけでなく、「聞く」機能を強化し、さらに開発者のモチベーション維持・向上にもつながる取り組みに昇華しており、とても好印象を受けた。
次回の祭りも一緒に盛り上げよう!
「展示会はお祭りである」と揶揄されることもあるが、それで良いのだ。何が悪い。お祭り=内輪のバカ騒ぎと見るのは短絡的で、一面しか見ていない。リード獲得手段としてしか見ないのも同様だ。お祭りだからこそできることがあり、通常業務の日常に刺激を与える非日常を作り出せるのだ。その非日常をいかに有効活用するかが重要なのだ。
祭りを盛り上げるには、主催者が頑張るだけでなく、各出展者も今以上に色々と取り組まなければならない。来場者が少ない、減ったというが、三菱電機ブースは今回も黒山のひとだかりができて大盛況だった。それは大手企業だから、出展内容が優れているからだけではない。商社・販売店と協力し、費用とコストをかけて全国から顧客を招き、相当な努力をしている。その結果なのだ。
また横河電機とアズビルは共同でアンケートを実施した。競合同士が手を取り合い、一緒になってユーザーの声を聞き、次に必要な技術などを探っていた。これもお祭りの場だからこそできたもの。自分たちの製品を見せるだけでなく、来場者を楽しませる、興味を惹くような取り組みがもっと大事なのだ。
IIEFSという同じ船に乗るもの同士、呉越同舟でもギブアンドテイク、協力して一緒に盛り上げていくことが必要。もちろん各社も色々と尽力しているとは思うが、盛り上がっているブースや企画に対して指をくわえて眺める、またはそのおこぼれを拾うのではなく、同じお祭りを盛り上げる仲間としてもっと柔軟に色々と取り組まなければならないのだ。
次回は2027年11月24日から26日から開催されるという。弊社は今回同様、出展し、ステッカーコレクションも実施する。今回以上の集客や告知も行う。計測制御、FA業界の底力を見せつけてやろう
ものづくり.jp株式会社 代表取締役社長 兼 オートメーション新聞 編集長 剱持知久
-
フジクラ、「Fujikura News」11月号を発行 新型光融着接続機や4列B2Bコネクタなどを紹介
-
IIFES2025 盛況裡に閉幕 来場者数は4万5324人 次回は2027年11月24〜26日に開催