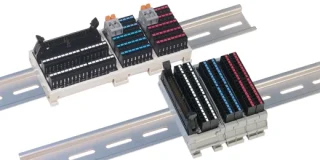現役生産技術シマタケの 「電気エンジニアのツボ」出張版⑭工場DXの現実とこれから ~変化を恐れずに~

ここ数年、現場で仕事をしている中でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が一気に増えました。私自身、工場や設備に関わる中で、アナログな作業や紙の帳票がまだまだ多いことを痛感しています。だからこそ、設備データのリアルタイム可視化や帳票の電子化といった取り組みは、現場の負担を減らし生産性を上げる上で効果的だと感じています。最近ではAIによる異常検知や予知保全まで実用段階に入りつつあり、「いよいよ工場もここまで来たか」と思わされます。そんなDXの流れの中で、実際に感じていることや悩みを今回のコラムではお伝えしたいと思います。
いざ自分がDXに関わる側に立つと、理想と現実のギャップに悩む場面が多くあります。とくに費用面は大きな壁です。内製化できるところは自社で対応している部分もあるのですが、AIやIoTを使った仕組みを導入しようと思えば、数百万円〜数千万円の投資が必要になることもあります。実際に私が勤務している企業でも「その金額でどんな効果があるの?」「費用対効果は?」と上長に問われることがあります。きっと似た経験をされた方も多いのではないでしょうか。
DXの代表例として設備データの可視化がありますが、一般的な設備投資と違い、導入直後から即効性があるわけではありません。まずはデータを集め、分析し、対策を検討する段階が必要です。数字で成果を示しづらいため社内の理解を得にくく、私自身「これは良い取り組みなのに、どう説明すれば伝わるだろう」と悩んできました。
さらに、DXに関係のあるプロジェクトに参加したり現場を回ったりしていると、「DXに取り組むこと自体」が目的化し、本来の目的である業務改善が置き去りになるケースも目にします。言葉だけが先走り、現場との温度差が広がると、むしろ負担が増えることさえあります。また、DXによって現状が大きく変わる可能性があるため、進めたくても賛同を得られず足踏みしてしまう場合もあります。
こうした経験から、企業にはそれぞれ歴史や文化、体力があることを改めて感じています。だからこそ私は、「身の丈に合ったDX」を進めることが重要だと考えています。一部の工程の可視化から始めても良いですし、帳票を段階的に電子化するだけでも現場改善は進みます。最近は安価で導入しやすいツールも増えてきましたので、スモールスタートで取り組みやすい環境が整ってきたと感じています。
最後になりますが、いま製造業は、人口減少・人手不足・高齢化といった課題に直面し、従来のやり方だけでは厳しい状況になりつつあります。求人を出しても以前ほど人が集まらないと感じることも増えました。だからこそ、DXは“やったほうがいい”ではなく、“やらないと厳しい”段階に入っていると感じています。
とはいえ、長年続いてきた習慣を変えるのは簡単ではなく、反発が出るのも自然なことです。私の経験では賛否はあるものの、トップが明確な意志を示し、現場と対話しながら進めていくトップダウン型のアプローチが、結果的には最も成功しやすいと感じています。
焦る必要はありません。小さくても一歩を踏み出すこと。その積み重ねが確実に未来を切り開く力になります。私自身もそう言い聞かせて、日々DX関連の業務に取り組んでいます。
【著者プロフィール】
シマタケ

共働きの子育て会社員。工場で15年間働く電気エンジニア。現在は某製造メーカーの生産技術担当。エネルギー管理士、第3種電気主任技術者、第2種電気工事士
機械保全技能士電機系2級、工事担任者(現DD第1種)、2級ボイラー技士、消防設備士(乙6、7)、危険物取扱者(乙4)など多数の国家資格を取得。心理学を勉強中でメンタルケア心理士、行動心理士も取得。
「電気エンジニアのツボ」でブログとYoutubeで情報を発信中
-
ダイヤトレンド、産業用16ポートスイッチングハブ「DEH-GTX16C」発売 小型・低価格化、PoE対応モデルも
-
アイリスオーヤマ、中国・深圳市に「中国R&Dセンター」を開設 IoT、ロボティクス等の研究・開発を加速