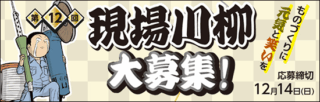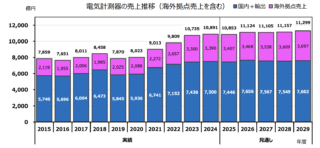- コラム・論説
- 2023年2月1日
【製造業・世界と戦う担い手づくり エキスパート待望 (108)】中堅やベテランに対し挑戦させる 市場に無関心で内向きな若手技術者を外向きに変える特効薬
会社員の立場でノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏。雑誌でのインタビューの中で印象に残っている言葉があります。
それは、「市場で一体何が求められているのかという問いに対して、技術者だけで”たこつぼ”のように対応した」ということが日本のものづくり競争力低下の一因ではないか、という部分です。
つまり特定の専門領域に偏った技術者だけでは似たような考え方しかできないため、より多様な専門性を有する人員構成にすることが必要では無いか、という問題提起と理解しています。
実際、若手技術者を部下に持つリーダーや管理職は、「最近の若手技術者は外に出ないだけでなく、外である市場に関心が無く内向きである」と感じることがあるかもしれません。今回は技術者がこのような考え方をする背景について触れた後、企業の現場で対応すべきことについて考えてみたいと思います。
特定の専門領域という”内”に閉じこもるのは若手技術者だけではなく、技術者全体の課題
まず技術者を含む”技術職固有”の課題から考えてみます。リーダーや管理職が若手技術者に対して内向きであると感じる課題です。この基本にあるのは、知っていることこそ正義という考え方が根底にあることから、知らないことに対して必要以上に憶病になることがその一因です。
知らないことは、知らないで一つひとつ理解を積み重ねればいいだけなのですが、それがわかっていてもできないのが技術者の難しいところです。しかし、盲点となっているのはこの課題が若手技術者に限ったことではなく、中堅やベテラン技術者にも共通していることです。
田中耕一氏も触れている異業種技術交流の重要性
上記のような背景を踏まえてか、先述の田中耕一氏も「異分野融合で多様性を広げる」という表現で、異業種技術協業の必要性を唱えています。
これは私自身が様々な業種の企業の技術者指導をしていても感じることで、技術者は自らの知っている技術領域に対しては活発である一方、その一歩外に出ることについては躊躇する傾向にあります。
しかし特定の技術で、新しいものを創出する、課題を解決するということが困難である現代において、異業種技術協業によって異なる技術領域の強みを融合する考え方が不可欠と言えます。これらの重要性は、リーダーや管理職クラスの方であれば認識しているケースも多いかと思います。しかし、実際には前進できない状況となっている可能性もあるでしょう。
過去の成功事例にしがみつく中堅、ベテラン技術者達
過去のやり方、過去の成功等、経験のある中堅、若手技術者達は過去へのこだわりがあります。特に技術職である技術者は、このこだわりが強い傾向です。過去の経験が重要であり、それが技術的課題解決や新技術創出に役立つ可能性もあるでしょう。
しかし、多くの場合は当時の時代背景といった自らの経験を形作る外的要因に対する客観的視点が不足しているため、主観的視点で”のみ”物事を見ようとしている可能性も捨てきれません。
これは心理学でいう”現状維持バイアス”の一つですが、新しい挑戦よりも現状維持の方がリスクが低いという考えが根底にあるのです。
これが厄介なのは、「中堅、ベテラン技術者が過去の経験を若手技術者に強制し、若手技術者が挑戦して実体験を獲得する機会を失わせる」ことです。組織である以上、中堅やベテラン技術者の言うことは暗黙的に、もしくは明確に権限があるというのが原因の一つだと考えられます。
いずれにしても若手技術者が何かやろうとしても、それを必要以上に止めようとする中堅、ベテラン技術者の存在が、若手技術者の様々な言動を制限していることを、リーダーや管理職は理解しなくてはいけません。
内向きである若手技術者を変えるには、中堅、ベテラン技術者から変える
では内向きである若手技術者をどのように変えるべきか。その第一歩は若手技術者ではなく、「中堅、若手技術者が外に目を向けていることを若手技術者に見せる」ことになります。
–若手技術者の指導役であり、重しともなり得る中堅、ベテラン技術者の意識改革が重要
若手技術者を抑え込んでしまうかもしれない中堅やベテラン技術者”自身”が、「内向きでないということを行動で示せる」ことが重要です。
自分自身で内向きでないことを示せなければ、若手技術者達が内向きから外向きになることは難しくなります。少なくとも技術的業務で身近にいる中堅、ベテラン技術者達が、若手技術者と議論、または後押しできるようにするのが、リーダーや管理職の役割なのです。
中堅やベテラン技術者が脱内向きを実践するには技術情報発信から
具体的な話に入っていきます。内向きな若手技術者達が外に目を向けるようになるため、まず中堅、ベテラン技術者に対してやらせるべきことは、「技術情報発信」になります。
自社、もしくは中堅、ベテラン技術者の強みである技術を社外に技術情報として発信するのです。中堅やベテラン技術者の方々において、情報発信するのに必要な知識や経験は十分でしょう。
しかし、実際に発信をしようとするとうまくいかないケースもあるはずです。ここでよく生じる問題は、どこまでが機密情報か不明であることに加え、予備知識のない人に理解してもらう情報発信方法がわからないことです。
機密についてはコンプライアンスを重視する企業ほど悩むことが多いようです。ここでのポイントは、「技術的な強みを積極的に発信する」ことにあります。細かい技術の内容を発信するというよりも、「その技術によってどのような”課題を解決”できるのか」ということを発信すべきです。
このような情報を機密にする必要は無いはずですが、それこそ”たこつぼ”の中で議論していた技術者達は、自分の技術の強みに加え、どのような課題を解決できるのかを、客観的視点から明文化することができないのです。
本点を中堅やベテラン技術者に考えさせるという意味でも、技術情報発信というのは大変重要な取り組みとなります。予備知識のない人に理解させるために文章構成を考えるのは、”技術者の普遍的スキル”の根幹である「論理的思考力」鍛錬の最適な訓練となります。
知っていることこそ正義という専門性至上主義は、相手の状況に考慮して話をするという視点を曇らせる傾向にあります。「こんなことも知らないのか/理解できないのか」という言動は典型例です。
しかし、実際には技術というのは顧客が居て、その顧客が評価をすることによってはじめてお金を創出できます。顧客が技術的な内容をすぐに理解できるとは限りません。
上述の通り、外から見る方々は「その技術の強みと課題解決力」を見て初めて価値を理解できるのです。技術力には問題ないであろう中堅やベテラン技術者こそ、技術情報発信のやり方を知るべきでしょう。
技術情報発信の経験を持つ中堅、ベテラン技術者は若手技術者の内向きの考え方を修正する力がある
中堅やベテラン技術者が対外的に技術情報発信ができるようになれば、内向きの課題と外に目を向ける重要性、並びに具体的なやり方まで若手技術者に助言、指導できるようになります。このようにして、チーム全体として外に目を向ける文化を醸成していくのです。
若手技術者を育成するには、中堅やベテラン技術者から考え方を変えさせる。チームの文化を変えることは大変な労力ですが、中堅やベテラン技術者に対してチャレンジさせることも、若手技術者を即戦力化するためには時に必要であることをご理解いただければ幸いです。
【著者】

吉田 州一郎
(よしだ しゅういちろう)
FRP Consultant 株式会社
代表取締役社長
福井大学非常勤講師
FRP(繊維強化プラスチック)を用いた製品の技術的課題解決、該関連業界への参入を検討、ならびに該業界での事業拡大を検討する企業をサポートする技術コンサルティング企業代表。現在も国内外の研究開発最前線で先導、指示するなど、評論家ではない実践力を重視。複数の海外ジャーナルにFull paperを掲載させた高い専門性に裏付けられた技術サポートには定評がある。
https://engineer-development.jp/