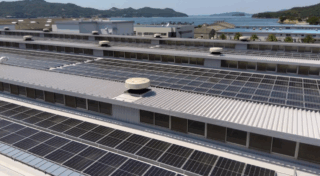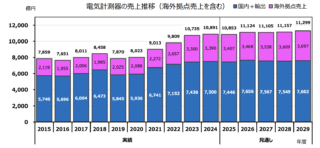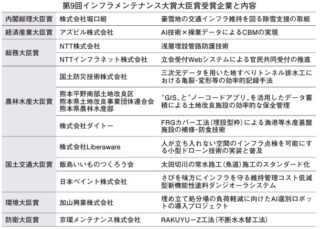- 新製品/サービス
- 2022年12月2日
【We love Automation!(Vol.5)】時給10円アップ

今から37年も前の話ですが、学生だった私はアルバイト先にハンバーガーショップを選びました。その店舗の営業終了時刻は22時で、そのあと閉店作業で厨房の片付けがあります。特に張り切っていたわけではないのですが、私の拭き掃除を見た店長がえらく褒めてくれた記憶があります。どうやら他のバイトの学生は、最低限拭いて終わりにしていたそうです。
当時は今よりも物価が安く、私の時給は750円でした。半年くらい経って私の仕事ぶりを見た店長が時給を上げてくれたのですが、+10円で760円になりました。当時から私は給料のために仕事をするというよりは、楽しそうな職場を選んだり、仕事そのものを楽しむことを重視していたのだと思います。
もちろんアルバイトの目的は対価として金銭を得ることで、当時とても高価だったパソコンを買うために必要なことでした。とはいえ時給を少しでも上げるために努力していた訳でもなく、給料は出たなりという感覚、つまりあまり深くは考えていなかっただけなのだと思います。
時代は変わりまして、現代では「仕事をすることで自分がどれだけ成長できるのか」ということに注目が集まっていると言われています。学生が就職先を選ぶとき、どの会社が自分を一番成長させてくれる、あるいは自分が一番成長できそうな環境なのかを見極めるというのは難しい課題です。世間の社会人の過半数は「思ったほど良くなかった」「仕事がつまらない」と感じているのではないでしょうか。
というのも、会社の規模が大きくなるとどうしても組織を細分化し、それぞれに役割と責任を定義してコントロールする必要があるからです。もし各部門が好き勝手に動き出すと、同じような仕事を複数の部門がやっていたり、反対に誰もやろうとしない抜け穴ができたり、およそ有機的に統制が取れているとは言えなくなります。そして何のために各部門が存在するのかが不明瞭になり、やがて会社としての存在意義が不明瞭になってしまいます。
そのため、大企業では官僚制を敷いて各部門の役割を明確に定義して統制を取ろうとしまが、それでは決められたことからの逸脱が困難になります。また共通のルールですべてを統率しようとし、部門によって異なる事情を吸収することができず、面白くもなければそれほど効率的でもない、という組織ができあがってしまいます。
もちろんそのような組織でも、過去に決められたルールの背景を深掘りし、その環境なりに自分を成長させることは可能です。しかしそれができるのはごくごく限られた人だけで、多くの方は決められた枠の中で必要最低限の仕事をすれば、大企業なりに高い水準の給料が得られますから、それで良しとするでしょう。
私にとって「自分が一番成長できそうな会社」を選ぶうえでその最も重要な項目は「良いコミュニケーションが取れるかどうか」「社員の方が楽しそうかどうか」だと思います。組織や自分の役割を超えた話をすることが歓迎されるのか、疎ましく思われるのか、その環境の違いです。誰が言ったかということは全く関係なしに、良いものは良い、違うものは違う、自分の間違いを素直に認め、相手の正解を称えることができれば「良いコミュニケーション」が取れている証拠です。
あと欲を言えば、そこに優秀な人が揃っていれば申し分ないでしょう。スタートアップのような小さな組織では、上記の「良いコミュニケーション」が成立しやすいのですが、人数の少なさ、経験の浅さから、優秀な人はごく限られてしまいます。やはり選手層の厚いチームに参加してプレーした方が、間違いなく刺激になります。
しかし、優秀な人というのは外部から集めて揃える必要はなく、自分自身がその優秀な人になろうと努力するのが一番です。そのためにも前述の「良いコミュニケーション」が必要になり、その中で一つ一つの小さな事象に対して常に正解が何か、ベストな選択が何かを追い求めるようにします。それは決して時給を10円上げるためでも残業手当を増やすためでもなく、自分の成長のためなのです。
◆湯口 翼(ゆぐち たすく)

1967年生まれ。大阪府出身。2002年に産業用センサメーカーのオプテックス・エフエーに入社。開発グループで新製品の開発に携わり、ローコストな印字検査専用の画像センサをはじめ、画像処理用LED照明コントローラやIO-Linkマスタなど画期的な新製品を多く生み出す。2008年に取締役、2024年に代表取締役社長に就任。