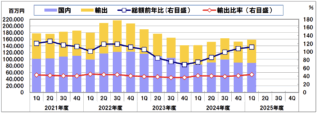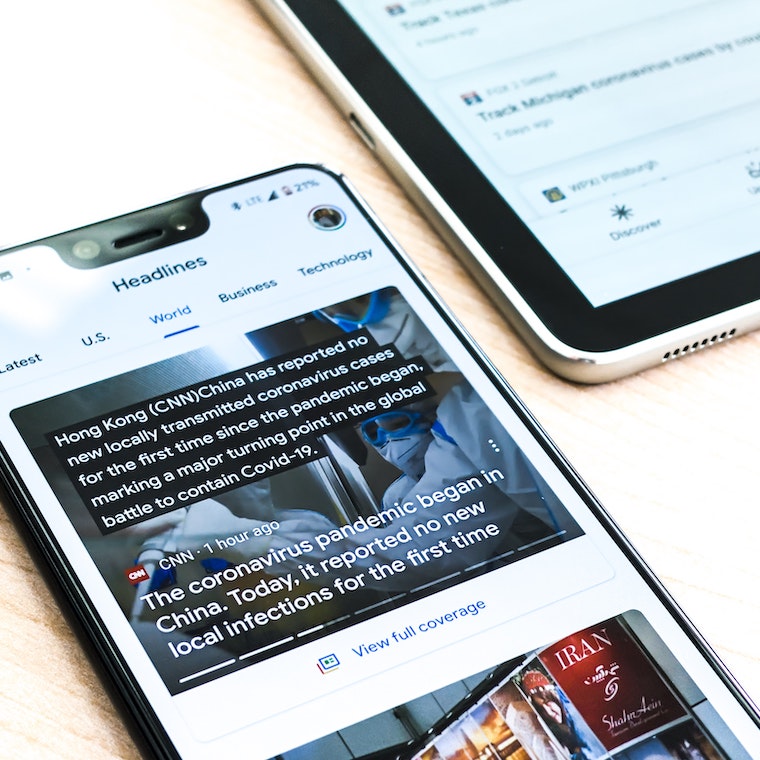マンネリ上等 飽きちゃダメだ ホンモノは色褪せない
志村けんさんが座長を務める舞台に出演していたダチョウ倶楽部は、ある日、定番ギャグに飽きてしまい、ある公演ではやらなかったそうだ。それを見た志村さんは「なぜやらなかったのか、自分が飽きたらダメだ。あれは面白いのだから、真剣にやれば必ずウケる」と叱ったという。ダチョウ倶楽部はそれを受けて次の公演でいつものギャグを披露したところ大爆笑をさらい、改めて志村さんの凄さを感じたそうだ。
志村さんは常々「マンネリ上等。飽きちゃダメだ」と言っていたそうだ。確かに志村さんのキャラクターは息が長い。代表的なひとみ婆さん、バカ殿、変なおじさんを最初に見たのは、何十年も前だ。それが亡くなる直前まで、昔と変わらぬ姿がテレビで流れていた。やってる事はいつも変わらない。展開は読めてしまう。しかしそれが面白い。キャラクターや展開を飽きずにやり続け、逆にそれが楽しみになるまで昇華する。まさに偉大なるマンネリ。本物は年を経ても色褪せない。それどころか年を経るごとにその価値は高まっていく。志村さんはそれを体現していた。
日本はテーマづくりやイメージ戦略に弱いと言われるが、今もオムロンの「SINIC理論」と、三菱電機の「e-F@ctory」は真に優れたものだと思っている。SINIC理論は、技術と人と社会が相互に影響しあって進化していくという考え方で、1970年に現在の社会情勢を正確に予測し、近年再注目されている。e-F@ctoryは、いち早く「工場のすべてをつなげること」に着目し、その重要性を説いた。両社の成長の源泉にこれらがあるのは間違いない。しかし残念なのは、いずれも今は表舞台になく、情報発信も減り、ひっそりと目立たない。もちろん今も大事にし、取り組んでいるのは知っている。しかし今のFA事業のなかでそれらが話題に上ることは滅多にない。もし両社がSINIC理論やe-F@ctoryの文脈に製造業とFA事業を乗せて語り続け、製品サービスを展開していたら今はどうなっていただろう。デジタル化やDXの必要性がもっと理解され、浸透しているifの世界が実現していたのではないだろうか。本質をしっかりと捉えているものは、時代を超えて受け入れられる。飽きやマンネリを恐れず、自信を持ってやり続ける、言い続けることが大事なのだ。