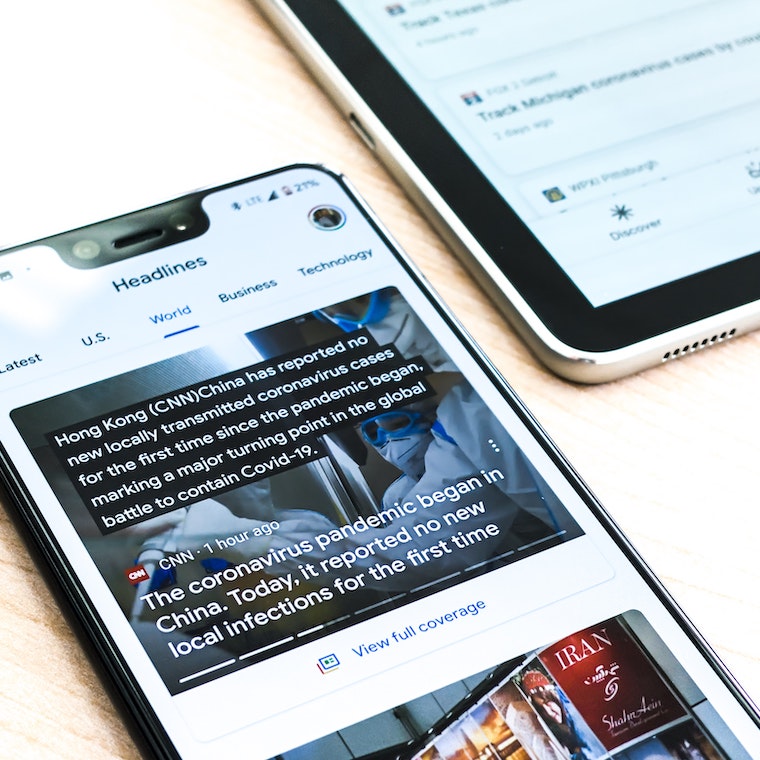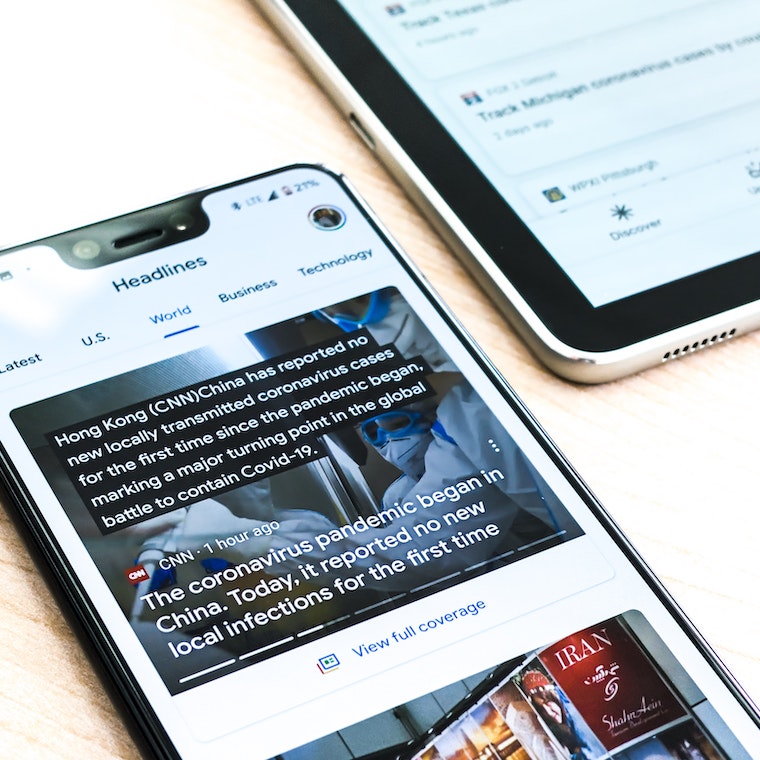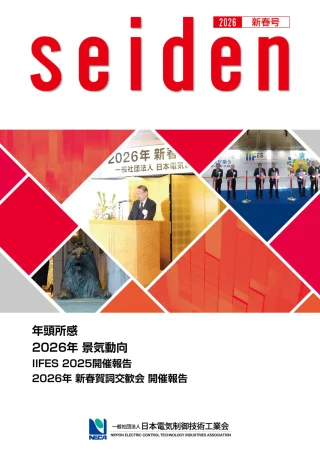- コラム・論説
- 2022年7月27日
【製造業・世界と戦う担い手づくり エキスパート待望 (109)】技術者育成を行うには技術専門性は必要か
今日のコラムでは技術者育成を行うために専門性が必要かということについて考えてみたいと思います。
技術者育成と一般的な人材育成は今でも区別されにくい
いまだに人材育成というとプレゼン力、コミュニケーション力、チームビルディング等の一般推進業務に関するもの、モチベーション向上などの業務推進の動機付けに関するもの、リスキリングをはじめとしたトレンドに関する基礎知識習得といった、一般従業員向けのものが多いのが実情ではないかと思います。
当然ながら前半で述べたことは日常業務のベースとなるため不可欠ですが、技術者としての特性が考慮されていません。また、リスキリングは実務の末端として仕事をすることを想定していることも多く、誰でも当てはまるわけではありません。
そして技術者を含む技術系社員の教育も見受けられますが、こちらは特定の技術専門性の教育と結び付けられてしまうことが多いようです。当然ながら実務に活用する内容であれば妥当ですが、多くの場合は知識の習得を目指す学校教育の形態となっている印象です。企業に勤める従業員の教育としては残念ながら適切とは言い難いと私は考えています。
そして何より問題なのは、一般的な人材育成では技術者をはじめとした技術系社員の考え方の癖や、特徴的な課題に目が向けられていないことです。
技術者育成を難しくする専門性至上主義
技術者育成において真っ先に理解しなくてはいけないのは、技術者の多くが専門性至上主義へのこだわりを持っているということの事実です。これが技術者育成を難しくしています。
何故でしょうか。技術者達は専門性至上主義に基づき、「技術者育育成を担当する人物はどのくらい技術がわかるのか」を見極めようとします。個人差や意識、無意識の差はありますが多くのケースに当てはまります。そして、技術的専門性が無いと見るや否や、「とりあえず話は聞くが、心の底では納得しない」という応答になってしまい、どれだけ優れた教育を行ったとしてもそれが身につかないことが多いのです。
こちらも当然ながら個人差がありますが、企業としては折角時間やお金を投資して技術者育成に取り組んでいるため、技術者たちの成長に結びつかなければ投資損となってしまいます。
技術者の信頼を得るためには育成相手の技術者に共感できる柔軟性が重要
上記の課題を克服するため、技術者育成を目的に技術者の指導を行う方々に求められるのは、「相手の技術に共感できる柔軟性」となります。
その技術は素晴らしいなどと褒めちぎるのではありません。技術的な議論を展開した時に、「それは○○ということですか」といった確認事項や質問を投げかけるのが一例です。
このような言動はあなたの技術に興味がありますという意思表示と受け取られます。技術者は専門性至上主義を掲げるが故に、自らの技術的議論に興味を示すか否かに敏感に反応します。このような応答を通じて相手の技術者の信頼を獲得する。これが技術者育成を行う人物に真っ先に求められる資質と言えます。
技術者育成を行う自分つに技術専門性は必要か
そして本題の部分になります。結論から言うと、技術専門性よりも技術を学び続けようとする向上心が必須となります。技術者育成を行うにあたっては、仮に同じ企業であったとしてもその技術者の実務で用いる、または得意とする技術領域は異なることが多い。
それらすべてを知るというのは不可能です。むしろ、「知らないなりに自ら調べ、自分なりに議論についていこうとする」という育成相手の技術者に対する敬意の方がはるかに重要です。このような姿勢は技術者にとって信頼という大きなポイントを与えることになります。
このように技術者育成を行うには、まず自らが学ぼうとする姿勢を持ち続けるということが重要なのです。
技術者育成を行う人物がまず取り組むべきは数学への興味保持
では技術者育成を行う人物はまず何から取り組むべきでしょうか。一言で言えば、技術者の普遍的スキルの一つであるグローバル技術言語力の強化です。一言で言ってしまえば数学です。
ただし、ここでいう数学というのは学校教育の数学というよりも、育成対象の技術者が実務推進するにあたって活用する理論に関する数学とご理解ください。
技術者育成に取り組む人物が数学が苦手、もしくは数式が嫌いということでは本当の意味で戦力になる技術者を育てることができません。最大の理由はただ一つ。「定性的議論、感覚論が残るため技術の本質である理論に到達できないから」です。
多くの技術において、最後は数式で現象や事実を説明する理論が存在します。ここをよりどころにするよう技術者を育てない限り、その技術力は必ず頭打ちになります。本質を理解できていない故に応用がきかないからです。
技術者育成の日常でも数学を積極的に取り入れる
これまでの話を踏まえ、技術者の育成においては適宜数学的な議論を誘発することが望ましいです。このことから、私も顧問先企業での技術者育成に関連した日常支援では数学の話を適宜入れるよう心掛けています。
最近のコラムでも、公差や誤差の積み重ねということを事例に二乗和を取り入れるという技術者育成の事例を紹介し、また別のものとして同等性の評価に検定を用いることも述べました。
このような地道な取り組みが、技術者育成で成果を出すカギとなります。いかがでしたでしょうか。技術者育成を推進するには、受け手である技術者以前にその育成を担当する人物にも求められるものがあることをご理解いただけたかもしれません。各企業でも技術系社員の教育担当に求められる姿勢としてご理解いただければと思います。
一般的な人材育成ではなく、技術者のための技術者育成を適切に進め、企業に勤務する技術者が一人でも成長し、企業の成長の源泉となることを望みます。
【著者】

吉田 州一郎
(よしだ しゅういちろう)
FRP Consultant 株式会社
代表取締役社長
福井大学非常勤講師
FRP(繊維強化プラスチック)を用いた製品の技術的課題解決、該関連業界への参入を検討、ならびに該業界での事業拡大を検討する企業をサポートする技術コンサルティング企業代表。現在も国内外の研究開発最前線で先導、指示するなど、評論家ではない実践力を重視。複数の海外ジャーナルにFull paperを掲載させた高い専門性に裏付けられた技術サポートには定評がある。
https://engineer-development.jp/