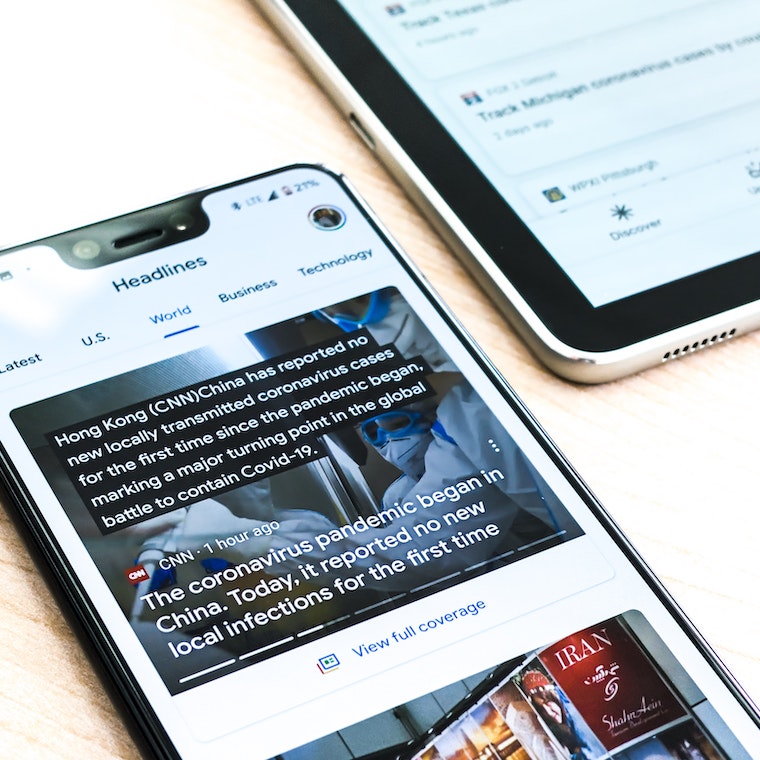令和の販売員心得 黒川想介 (143)増える人や物、管理の合理化 新たなアプリ探し出す営業を
西暦は時代の区分を「世紀」で表現する。日本には「元号」があるから、世紀と元号の両方を使って時代を区分できる。世紀や元号が変わったからといって時代の様相が急に変わるわけではない。技術の蓄積による価値観の変化が後になって比較できるようになり、「何々時代はこうだった」とか、「何世紀は何々の時代だった」と言う表現をすることになる。日本の元号は、そういう点で世紀だけの区分よりきめ細やかに表現ができるから、時代背景やその時代の出来事が伝えやすい。
各時代の歴史を知ることが大切なのは、その時代の背景を背負って歴史はどのような動きを見せてきたかを知ることができるし、似たような背景があれば参考にできるからである。
これまで述べてきたように、FA営業にも歴史がある。現在主流になっている営業戦法と言える活動は、平成期に出来上がった営業である。それは昭和期の営業とは違う。背景にあるものは「マーケットの違い」である。制御マーケットの草創期から次第に大きく成長していくときの営業活動と、マーケットが大きくなって安定したときの営業活動は全然違う。その違いの根本にあるのは、「顧客の自動制御技術の成熟度の進み具合」である。その成熟度の進み具合に並行して、機能や性能の違う各種の制御商品が少しずつ増えていく。
昭和前期の営業は、顧客の変貌や制御商品の開発が影響して、「新規客獲得営業」がもっぱらであった。昭和中期は「マーケットの急成長」だった。この時の営業は、これまでも述べてきたが、簡単にまとめると、①次々に発売される制御商品のアプリケーションの探索、② 発見したアプリケーションを全顧客に横展開する活動、③増え続ける見込み客の新規開拓活動 である。顧客や見込み客は売り込みを受けた際、すぐに必要でなくても、話に聞き耳を立ててくれた。
昭和の終盤には制御商品の高度化・複雑化が始まった。そのため「難しくなった制御商品をいかにして売るか」と言う営業に変わり始めた。
平成期には、「居並ぶ自動機がある工場を目の当たりにする営業」となった。制御商品は高度化・複雑化の流れが続き、販売員の耳には、機械が並ぶ製造現場からの需要が案件として入ってくるようになった。マーケットは成長続け、昭和期全般とは違い、高いレベルで横ばいの安定したマーケットになっていった。それにともなって競合が激しさを増した。それに加えて、営業にパソコンが導入された。
こうした背景のもと、平成期の営業の完成形は、①案件の解決営業、②競合商品切り替え営業、③高度化・複雑化した商品の紹介営業 の3本立てで、「発生する商談テーマの進捗管理営業」となっていった。
令和になって7年経過しているが、制御機器や制御部品を扱う販売店営業は、平成期の営業の営業戦法とは変わっていない。そもそも制御機器や制御部品は、生産システムや機器を構成するコンポやデバイスである。したがって商品の性質上、システムや機械、機器に追随する商品であるから、平成期に完成している営業とそれほど変わっていないのは当たり前かもしれない。令和7年の営業戦法が平成期とはほとんど変わってないといっても、後年になって令和期の営業はこうだったと必ず言うようになるだろう。なぜならば、制御商品は大きく変わる事はないが、制御する対象が平成期とは一味違うものが出現しているからである。
平成期にFA営業が売り上げを上げようとして制御の対象にしたのは、機械設備や生産システム、あるいは機器類である。令和期は、社会や技術の質が変わる。それらの変化によってFA営業の得意のマーケットである合理化需要が、対象を変えて出てくる。つまりは、機械や機器の合理化だけでなく、人やもの、管理に関わる合理化が増える。そうなると昭和の前期や中期のように手探りで新たなアプリケーションを探す営業を始めた方が良いことになるのだ。
-
ダイドー、情報サイト「メカトロネット」サービス停止 模倣サイトへの注意喚起も
-
フエニックス・コンタクト 端子台「XT・XTVシリーズ」新しい接続体験を 新接続技術Push-Xテクノロジ【配線接続機器特集】