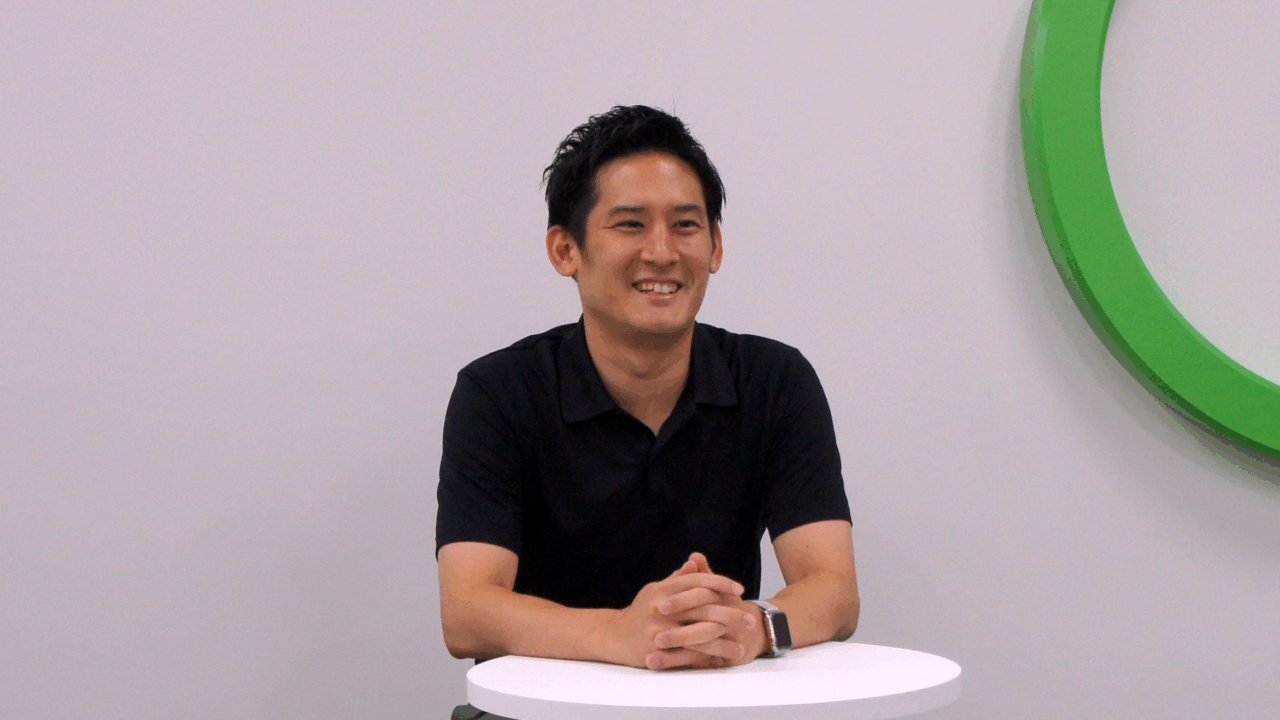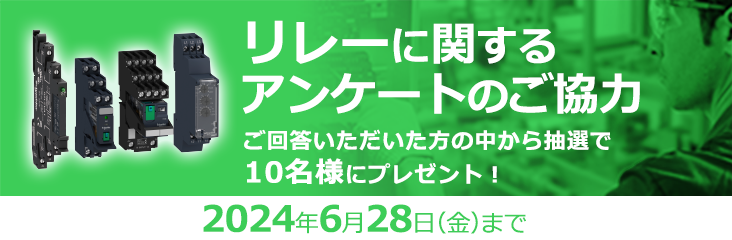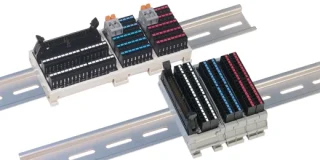【FAトップインタビュー】シュナイダーエレクトリック、製造業の生成AI活用への道を切り拓く最適アプローチ「SDA(Software Defined Automation)」とは?オブジェクト指向で作るフルデジタルのFAシステム

シュナイダーエレクトリック インダストリアルオートメーション事業部 商品企画部 扇芝 謙次 氏

生成AIの活用が今後のビジネスの成否を握るとまで言われるなか、製造業ではそれ以前のデータ活用の段階で苦戦していたりする。その原因となっているのが、ジャングル化して複雑になっている製造現場と、雑多な上に意味付けもされていない大量のデータ群。現場から集めたデータが活用できる状態になっていないという大問題がある。
シュナイダーエレクトリックは、この根深い課題を解決するための革新的なアプローチとして「ソフトウェア・デファインド・オートメーション(SDA)」を提唱。生産設備をハードウェア中心からソフトウェア中心のシステム構築とし、データや生成AIをフル活用できる真のデジタルシステムへの転換を推進している。
そんなSDAについて、シュナイダーエレクトリック インダストリアルオートメーション事業部 商品企画部の扇芝 謙次 氏に話を聞いた。
なぜ整ったデータが取れないのか?それは製造現場がジャングルだから
― ―製造業のデータ活用が叫ばれて久しいですが、言うほど進んでいない状況があります
当社では、現在の工場の制御システムの世界を、一言で「ジャングル」と表現しています。工場には何百、何千というコントローラーやデバイスがあり、それぞれ異なるベンダーが独自のソフトウェアや通信規格を使用しています。それらをなんとか繋ぎ合わせて、一つのシステムとして動かしているのが現状です。これは多種多様で個性的な植物が密集し、絡み合い、1つの森が形成されているジャングルそのものです。
― ―「ジャングル」とは、非常に的確かつ面白い表現ですね。
このジャングルの最大の問題は、各社の機器がハードウェアに強く依存したものとなっており、非常にクローズドで柔軟性・拡張性に乏しいという点です。実はこの状態が、データ活用のために必要十分な情報を持ち、かつ整っているデータを収集することを難しくしているのです。
生成AIが正しく賢い答えを出すためには、良質なデータが必要不可欠です。しかしジャングルの中のデータは、メーカーごとにサイロ化していて、どれだけたくさん集めても単なる数値や文字列の羅列でしかありません。これではいくらAIが賢くても何が何だか分かりません。せっかくの生成AIも宝の持ち腐れになってしまいます。これが製造業でデータ活用が進まない理由の一因であり、生成AIの活用とそのアプリケーション開発での大きな障壁となっています。
ハードウェアの呪縛から解放する「ソフトウェア・デファインド・オートメーション(SDA)」
― ―ジャングル状態を解決するために御社が提唱されている「SDA」とはどんなものですか?
「ソフトウェア・デファインド・オートメーション(SDA)」は、従来のハードウェア中心のシステム構築から、ソフトウェア中心の柔軟なオートメーションシステムへと移行するアプローチを指します。
これまでの装置設計は、各装置の構想設計の後、PLCなどのハードウェアを選定し、それらを動かすためにそれぞれ専用のソフトウェアプログラムを作り、それら各装置を組み合わせて全体のシステムとするというのが常識でした。
しかしSDAではその常識を覆します。全体システムの構想設計の後、複数の装置と各機能のソフトウェア設計を先に完成させ、その後、各機能を実行するために必要なハードウェアを選び、各ハードウェアに各機能をマッピングし、それらを組み合わせてシステムとします。
SDAでの主役はソフトウェアであり、ハードウェアは、極端に言えば「箱」のようなもの。ソフトウェアとそこで作ったプログラムこそが再利用可能な「資産」であると考えます。そのソフトウェアが動作する環境であれば、ハードウェアはどのメーカーのものでも構いません。ハードウェアの呪縛からソフトウェアを解放することで、真にオープンで拡張性の高いシステムを構築できるようにするのがSDAです。現在当社では、SDAとそれを具現化したソリューション「EcoStruxure Automation Expert」を展開し、普及に努めています。
ITでは当たり前の「オブジェクト指向」と「データコンテキスト化」をOTで採用
― ―SDAのメリットは?
SDAでハードウェア依存から脱却し、ハードとソフトを分離して、それぞれを資産として使えるようになることで、例えば装置の改修や移転などの時間と手間を減らすことができます。デジタルツインを複数の装置やラインにも展開でき、デバッグの効率化や早期の立ち上げを実現できるようになります。
また現在は装置や生産ラインの各工程を制御するために多くのコントローラや表示器が現場にありますが、SDAになると、例えばそれらがすべて現場にあるオンプレミスのエッジサーバーに集約し、コントローラや表示器の台数を減らすことができます。サーバー内に構築されたバーチャルPLCと各装置やI/O、コンポーネンツが通信し、制御するような世界が実現できます。
そのほか、ソフトウェア設計の脱属人化などにも有効です。
― ―データ活用に向けての有効性という面ではいかがでしょう?
先にも述べた通り、製造現場はジャングル化していて良質なデータを収集するのが難しいという問題があります。これによってデジタルツールとも連携しにくい状態がずっと続き、生成AIを活用するところまでたどり着くのを難しくしています。
それに対しSDAでは、ITの世界では既に主流となっている「オブジェクト指向」というプログラミング設計の手法をOTの世界に持ち込んでおり、SDAでシステムを構築すると、デジタルツールと連携しやすい形のデータを各機器や工程から集めることができるようになります。
具体的には、SDAではシステム設計をする際、モーターやコンベアといった現場の「モノ(オブジェクト)」単位で、それらを制御するプログラムと、それに関連するデータ(電流値、温度、稼働状況など)を一つの塊(オブジェクト)として、プログラムとデータがセットになったカプセルのような形として定義して設計していきます。
これが非常に重要なポイントで、従来のPLCではデータは単なる「D1」といったアドレスを持つ数値の羅列でしたが、オブジェクト指向でプログラムを作ることで、そのデータは「ラインAにあるコンベアBのモーターCの電流値」という、意味(コンテキスト)を持った「情報」になります。当社ではこれを「データのコンテキスト化」と呼んでいます。
この「コンテキスト化された情報」は、現場の制御層(OT)から、SCADAやMES、さらにその上の経営層が見るITシステムまで、意味が失われることなくシームレスに連携することができます。これにより、これまでデジタルツールに連携させるために、データサイエンティストが多大な労力をかけて行っていたデータのクレンジングや紐づけといった前処理がいらなくなります。
さらに、設計ルールが標準化されているので生成AIを活用したプログラム作成の自動化ができたり、すべてのデータに意味づけがしてあるので言語化にも適しており、生成AIを使った機能やサービスへの展開もしやすくなります。
誰もがデータと生成AIを使って現場を改善できる時代へ
― ―SDAで製造業の生成AI活用への道が開けると、どんな感じになるのでしょうか
例えば、これまで専門家しかできなかった高度なデータ分析が、生成AIを使うことで誰もが簡単にできるようになります。
工場長が自席のPCから、生成AIのアシスタントに「先月から第2ラインの稼働率が5%落ちているけれど、原因を特定して、改善策を3つ提案して」と問いかければ、AIは、現場のリアルタイムデータと、生産管理システム(MES)などのITデータを統合的に分析し、「モーターXの振動データに異常が見られます。予知保全のアラートです。また、その前工程の部品供給に30秒の遅れが頻発しています。これが原因と考えられます」といった風に、的確な回答を返してくれるようになります。
― ―まさにデータドリブンな意思決定ですね。
経営者から現場のオペレーターまで、それぞれの立場の人が、それぞれの言葉でAIと対話しながら、継続的な改善活動を行えるようになります。これは深刻化する人手不足という課題に対する一つの答えにもなると考えています。
また、生成AIでプログラムを作成することも可能になり、ラダー言語を知らない若いエンジニアでも高級言語の知識を活かしてFA業界に参入しやすくなるというメリットもあります。
オープンなエコシステムで業界全体の変革を目指す
― ―SDAを普及させていくためにどんな取り組みをしていますか?
SDAの考え方自体は「UniversalAutomation.org (UAO)」という、FA関連企業やユーザー企業、大学や研究機関などで構成される国際的な標準化団体が推進しており、当社もその一員として活動しています。UAOを通じて、メーカーの垣根を越えた共通のソフトウェア実行環境を普及させ、オープンなエコシステムを構築することを目指しています。
UAOは、SDAを、スマートフォンでいうAndroid OSのようなものへと発展させていきたいと考えていて、共通のプラットフォームの上で、各社がそれぞれの強みを活かしたアプリケーションやライブラリを提供し、ユーザーは自由にそれらを組み合わせて最適なシステムが構築できる、そうした基盤を整備することで業界全体の活性化を目指しています。
― ―今後に向けて
生成AIという強力な武器を製造業が真に使いこなすためには、まずその土台となるデータ基盤を整える必要があります。SDAは、そのための最も効果的で、現実的なアプローチだと確信しています。この新しい制御システムの考え方を広めることで、日本の製造業が直面する様々な課題解決に貢献していきたいと思っています。
-
【オートメーション新聞No.426】25年度上期 産業用汎用電機機器出荷3523億円 / 三菱電機 三相モータ事業譲渡 / はんだ付けコンテスト日本大会優勝者決まる / 鉄道技術展2025/など(2025年11月19日)
-
パナソニックインダストリー、タイ・アユタヤに多層基板材料の新棟建設 AIサーバ需要増に対応