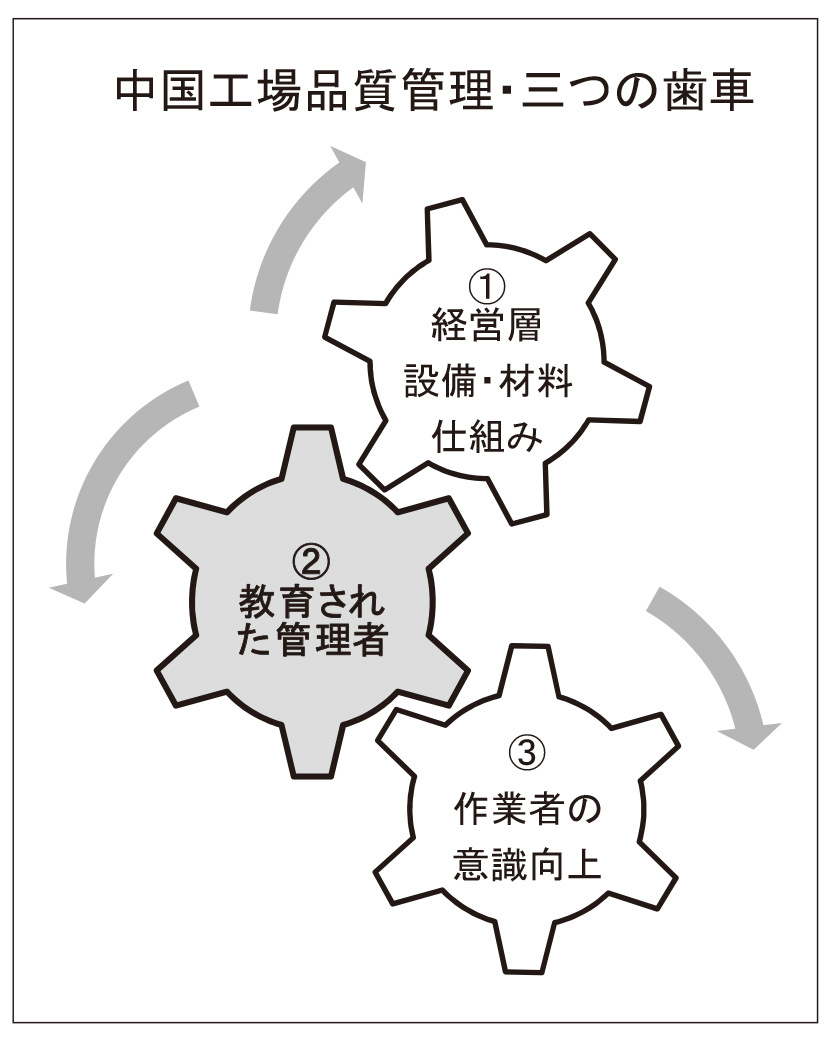【○○なカイゼン 第一話】偶然の産物と副産物 現場カイゼンの想定外 サイズ変更で売上向上
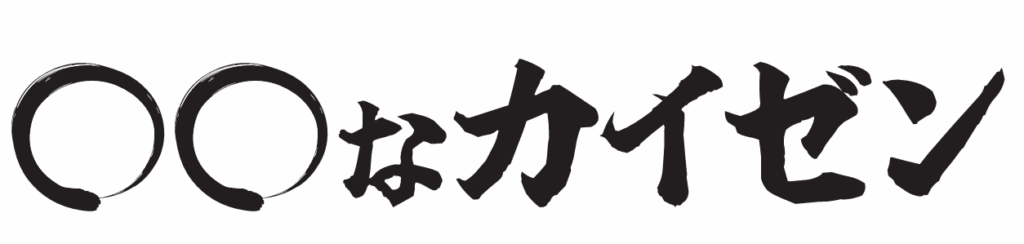
先回まで私が考えるデジタル化についてお話をして参りました。ここで一回このテーマを離れて、今回から私がこれまで経験した現場カイゼンの中で、特に印象に残っている内容をお話しさせて戴きたいと思います。現場で現物を前にして皆様とカイゼンをしていると、最初は全く考えもしなかったことが起きて、それがびっくりするような結果を生み出すということが珍しくないのです。このような状況が起こせるのは多様性のあるメンバーが共通の基盤に立って目標を共有化しているからこそだと思います。そして更にそのような機会を設けることによってより良い結果を生み出すことが可能なのではないかと考えています。
和菓子を作っているO社の現場でカイゼン会をしていた時のことです。商品が詰められた箱を袋に入れる作業を皆で見ておりました。袋の大きさが箱の大きさとあまり変わらず、とても入れにくそうで時間もかかっていました。しばらく見ているとどうしても入らないので袋を廃却したり、時には破れてしまうことも起きていました。
その場で、皆でいろいろな意見を出し合いました。そしてその中のひとつに、「袋を大きくすればいいんじゃないでしょうか」という意見が出ました。小さいのだから大きくすればいいのは当たり前ですが、誰もが現在の袋にも意味があると思っていますから、簡単に実現するとは思っていなかったようです。
しかしそこに同席していたデザイン担当の人はいとも簡単に「そうですね、やってみましょう」と快諾してくれました。これにはとても驚きました。デザインの変更は最も難しいモノといった気持ちがあったからです。
そして袋のサイズが大きくなりゆとりができたため、箱を入れる作業はとても楽になりました。袋の廃却もなくなり不良もほぼゼロになりました。これは当初の狙い通りでした。
このカイゼンによって当初の目的が達成されたのですから、これでよしと思っていたのですが、実はこのカイゼンには続きがありました。
袋のサイズを変えた時に多少のデザイン変更も行われました。少し大きく見えるようになったのです。その結果、お客様の目に留まるようになり、以前より少し売り上げが伸びました。これは偶然の産物と言えるでしょう。
更にこの話はこの続きがありました。売上が伸びたことによって商品の回転率も上がり、お客様の手元に着いた時の鮮度が上がり美味しいという評判が立ち、売り上げがもっと伸びたのです。これは偶然の産物から生まれた副産物なのではないでしょうか。
その時、私たちはリードタイム短縮をするために、中間在庫を減らしたり、工程を統合したりのカイゼンを始めようとしておりました。その矢先にこのようなニュースが入り、お客様に新鮮な状態で商品をお届けすることの大切さが伝わりそれからのカイゼンに更に力が入りました。
リードタイム短縮のカイゼン活動はその後協力メーカーも含めた全体活動へと広がり、すべての商品を対象に新鮮度が増し、O社の売り上げ向上に貢献しました。O社は新製品の宣伝はしますが、従来からある商品については特別な宣伝はしていませんでしたが、着実に売り上げが上がっていました。最初はその理由が分からなかったのですが、お客さまからの情報を元に、これも新鮮さが増したからだと分かりました。
現場カイゼンを皆でやったことで商品開発ができた事例です。

日本カイゼンプロジェクト 会長 柿内幸夫
1951年東京生まれ。(株)柿内幸夫技術士事務所 所長としてモノづくりの改善を通じて、世界中で実践している。日本経団連の研修講師も務める。経済産業省先進技術マイスター(平成29年度)、柿内幸夫技術士事務所所長 改善コンサルタント、工学博士 技術士(経営工学)、多摩大学ビジネススクール客員教授、慶應義塾大学大学院ビジネススクール(KBS)特別招聘教授(2011〜2016)、静岡大学客員教授 著書「カイゼン4.0 – スタンフォード発 企業にイノベーションを起こす」、「儲かるメーカー 改善の急所〈101項〉」、「ちょこっと改善が企業を変える:大きな変革を実現する42のヒント」など
一般社団法人日本カイゼンプロジェクト
改善の実行を通じて日本をさらに良くすることを目指し、2019年6月に設立。企業間ビジネスのマッチングから問題・課題へのソリューションの提供、新たな技術や素材への情報提供、それらの基礎となる企業間のワイワイガヤガヤなど勉強会、セミナー・ワークショップ、工場見学会、公開カイゼン指導会などを行っている。
■詳細・入会はこちら