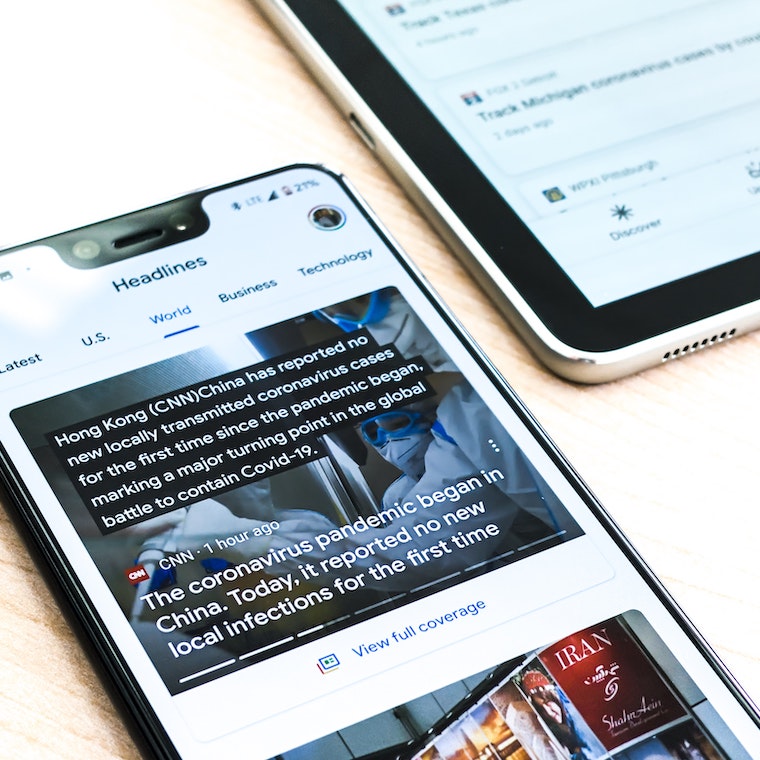日本の製造業における生産計画の実態 (8)
前回まで、欧米では当たり前になっている「シミュレーションソフトの活用」が、日本の製造業においては進んでいない状況をレポートしたが、実際に導入・成功している事例を紹介する。
シミュレーションソフトウェアの導入事例‥ニチバン(取材協力‥構造計画研究所)
1〓導入企業の事業概要
セロテープに代表される、独自の粘着・接着技術をベースに、医療・ヘルスケア、オフィス・ホーム、産業向けなど、多種多様な製品を製造・販売。
2〓導入前に直面していた課題
A‥生産管理が工場ごとに属人化されて共有できなかった。
B‥システムの導入が現場に受け入れてもらえない。
C‥計画作業に時間がかかり、計画サイクルが長くフレキシブルな需要に対応できていなかった。
D‥急な欠品等への対応のための計画変更は、製造設備の稼働予定や原材料・仕掛品の計画も考慮しなければならず、大きな負荷になっていた。
E‥計画担当者の定年退職や移動に伴う計画立案作業の引き継ぎが困難になってきていた。
3〓導入の経緯・導入後に得られた結果
本格的な導入を進める前に、まずはシミュレーションソフトウェアが有効に働くのかどうか、評価を行うことを目的としたプロジェクトチームを組織。
現行の生産計画の立て方は変えないが、隣でシミュレーションソフトウェアを活用した生産計画立案も並行して行い、現行の生産計画と同じレベルの精度が出せたかどうかの比較・検証を行った。
シミュレーション結果を現行の生産計画と比較すると、ほぼ同等の精度での生産計画が立てられた。
特筆すべきは、熟練のスタッフでなくても、ロジックの積み上げで精度の高い生産計画が立てられたということである。
さらに、シミュレーションの結果によると、このままの生産計画で行くと数日後に欠品が生じることが予測できた。現行業務のやり方には口出しをしない約束だったので、そのまま業務を続けていった結果、実際に欠品が生じた。
ここで伝えたいのは、まずはソフトウェアを使ったやり方を評価してみて欲しい、ということである。
現行業務をすぐに変えなくてもいいので、是非、将来に向けた投資として、評価するプロジェクトを立ち上げる機運が高まることを期待したい。
特に経営層の方には10年、20年先を見据えて検討されることをお勧めしたい。
次号では「シミュレーションによる効果」を掲載予定。
(つづく)