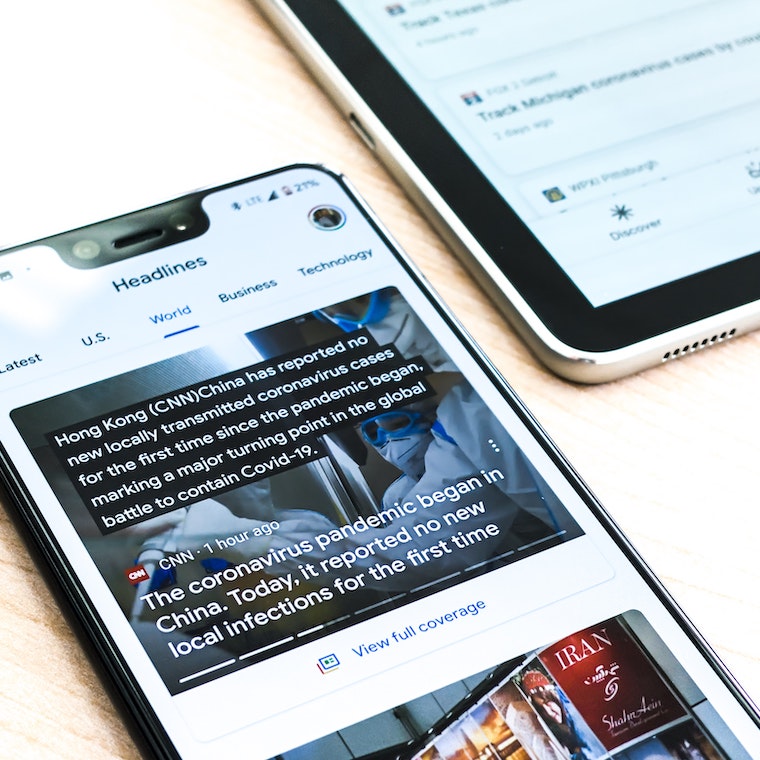- コラム・論説
- 2010年10月13日
令和の販売員心得 黒川想介 (136)製造現場の「潜在需要」は「外向き情報」活用が鍵に
「灯台下暗し」と言うフレーズを耳にする。これは身近な物事には意外に気づかないという意味で使われる。
FAマーケットが照らす需要は企業の設備投資に影響を受ける。どの企業も成長を目指しているから何らかの設備投資をする。だからFA業界は他業界に比べれば安定している。
その一方で、製造業はグローバル化していくから、国内工場の増設はそれほど期待できない。その上、意外と気づいてない事は、制御機器や部品を使用する新しい用途例があまり増えていないことである。ゆえに、国内の制御商品出荷はそれほどの伸びを示していない。
令和期は、IT技術によるデジタル化や資源に関する新しい価値観が製造現場にも入って、新しい生産の方法で合理化を進める動きが活発になる。そのような動きを踏まえて新しいアプリケーションを作る。新商品の開発が欲しいと同時に、FA営業は制御商品や部品の新しい用途の発見や工夫に力を入れてほしいところである。
実際に、販売員が耳にしている製造現場の動きには、数年前から生産設備のデータ取りの需要が多くなっていることや国内経済がデフレ脱却に向かっているせいもあって、御多分に洩れず、「人手不足に苦慮している」と言うようなことである。
こうした情報は、いつも顔を合わせる顧客からの入手であるから、前回述べた「内向き情報」に分類される。内向き情報は、販売員にとって都合の良い商談レベルに近い形で情報が入ってくる。このような内向き情報が入ってくると、販売員は商品を想定して売り込み活動する。見える化するためのデータ取りになるから、機械設備の電力、温度、振動等のセンサや通信機器、ロガー等の売り込みになりがちだ。また人手不足と聞けば、各種のロボット系商品の売り込みになる。
しかし、製造現場の動きには販売員が気づきづらく、「灯台下暗し」の潜在需要がある。潜在需要の元になる情報が「外向き情報」である。
外向き情報は、内向き情報と違って販売に都合よく加工された情報ではないため、違った景色が見える。外向き情報を発信する人の1人には、販売員がほとんど話をしたこともない、製造ラインを預かるライン長がいる。製造ライン長は、制御機器や部品を決めたり直接発注するわけでは無いから、販売員と接触する事は少ない。ライン長は生産設備を使って製品を作る作業者を指導管理して生産目標に責任を持っているし、生産性向上や品質を常に意識して合理化を進めようとする。その折に人の作業を機械化することが決まっているなら、生産技術のスタッフが中心となって動いている。しかし作業員不足が日常化していると嘆いているようなら製造ライン長は「何とかならないものか」と生産技術のスタッフに相談する。それを受けて生産技術のスタッフは、理想的な自動化設備を進めようとする。しかし実際には付加価値の問題や資金、その他の事情で話は前に進まない。このような状況に悩みを抱えている。
このような製造ライン長が大勢いることを販売員は知らない。このライン長が話す情報を外向き情報と言うのだ。
ライン長は、資金が必要になって大掛かりになる自動化や、プロセスの管理を大げさにシステム化するような正論的な解決を求めているわけではない。切羽詰まっているからなんとかしなければならないが、社内事情があって苦悩している。
そのような製造ライン長が、なぜ苦悩しているのかをよく知れば、そこにはビジネスチャンスがある。FA営業がマーケットにしてきたのは、そこに設備ありきの正解であるから、まだ設備が形になっていないと手も足も出さない。設備が形にり、こんなジグやアクチュエーターを作れば検出できるのではといったような気軽な話し合いをできるのは、裏打ちされた技術を持たない販売員なのである。